家づくりお役立ちコラム リノベーション 一覧
-
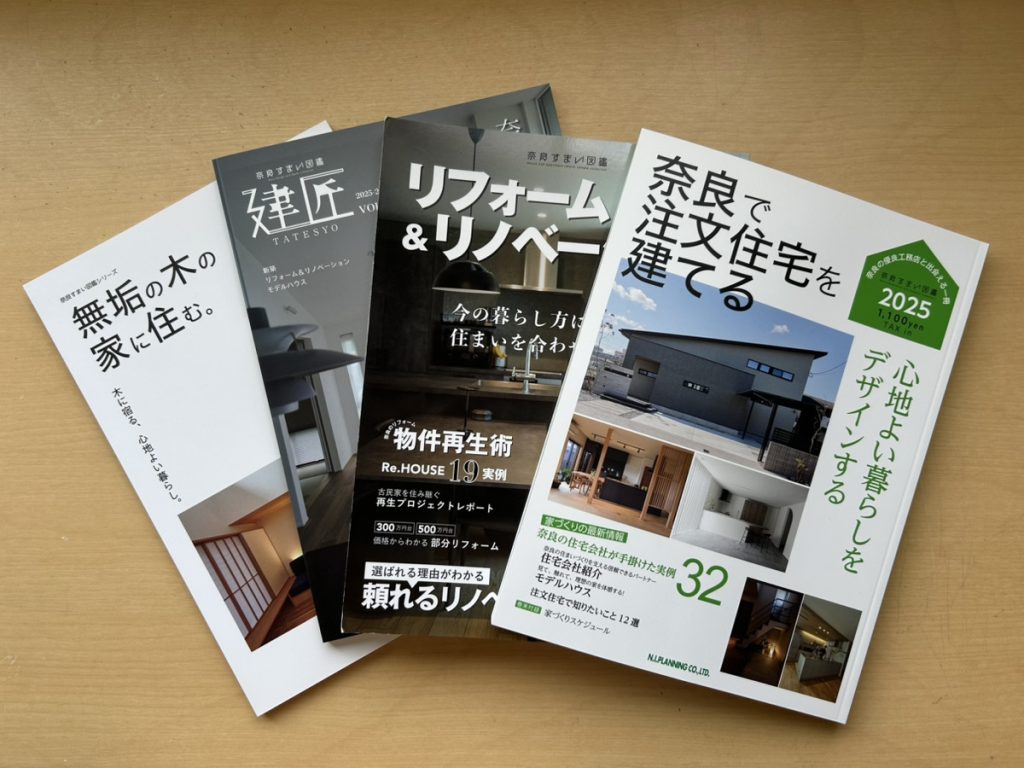
2025/08/22
奈良県の工務店に依頼する3つのメリットと会社選びで失敗しないコツ【新築注文住宅・リフォーム共通】
当サイト「奈良すまい図鑑WEB」では、奈良の地元に密着し、誠実にお仕事をされている工務店をご紹介しています。また、現在編集部では、年に4回、奈良の工務店情報や工務店が建てた家を紹介する雑誌「奈良すまい図鑑」を発行しています。今回は、そんな編集部だからこそわかる、「工務店の選び方」「工務店の違いについて」「会社選びで失敗しないための工務店を選ぶコツ」などをお伝えします! 新築注文住宅・リフォームを奈良県の工務店に依頼する3つのメリットは、【1】理想を現実にしてくれる自由度の高さ、【2】地元の会社ならではのフットワークの軽さ、【3】大手ハウスメーカーとは数百万~数千万円安い場合があるといったことが挙げられます。 メリット1、理想を現実にしてくれる自由度の高さ 注文住宅やリフォームなど、お施主様の理想を実現するため、決まった工法や設備メーカーの指定が無い場合がほとんどです。理想や希望と予算のバランスを取りながら、全体を組み上げていかれます。また工事が進んでいる途中でも、コンセント位置の変更や、造作家具の依頼など、すぐに対応してくれる柔軟さも工務店ならでは。 メリット2、地元の会社ならではのフットワークの軽さ 地元で仕事をされている会社だけあり、地域独特の市街化調整区域などの景観法はもちろん、地域のこまかな情報を熟知されているので、とても心強い存在です。そして、家を建てた後のメンテナンスや、ちょっとした住まいの不便をすぐに相談・解決できるのも地元の会社ならではです。 メリット3、大手ハウスメーカーとは数百万~数千万円安い場合がある 地域に密着している工務店では、テレビCMなどの大規模な広告宣伝費、毎年新卒を獲得するためのリクルート費、総合展示場への出展費といった予算を必要としない会社が多いため、消費者還元につなげやすいのです。 失敗しない!会社選びのコツ:工務店の違いを知る ・会社ごとの特長 各社により、得意な工法、テイストがあります。自然素材を用いた家づくりを掲げていたり、ホテルのような雰囲気のお家が得意だったりと会社のカラーはさまざま。とはいえ、どの会社も本当に柔軟で、「どんな家でも、かなえます」というスタイル。その臨機応変に対応できるスタンスが工務店の魅力の一つです。 ・どんなスタッフがいるか 奈良県内にある「工務店」という言葉が商号に入る会社でも、人員体制はさまざま。 最初の打ち合わせ・設計・工事まで、同じ担当者が全て担っている2~3名の会社もあれば、 窓口担当者・設計者・工務担当者、それぞれ分かれており、従業員も数十人いる会社もあります。 前者の場合は、即断即決してもらえる場合が多く、話もスムーズ。 後者の場合は、誰か1人が急な休みの場合でも、代わりに話を聞いてもらえるので、安心できます。 工務店の決め手とは ・理想の家のテイストを得意としているか 無垢の木の床と漆喰壁など自然素材をふんだんにつかった家。吹き抜けと大きな窓がある大空間リビング。ホテルのような玄関ロビーなどなど、自分たち家族がどんな家に住みたいのか、どんな暮らしがしたいのか、それを効率的にかなえてくれるかどうか。各社のWEBサイトやSNSで過去の施工例を確認したり、開催しているイベントに足を運んだりして、会社のことを調べましょう。 ・どんな人と出会えるか 注文住宅の家づくりは自由度が高い分、本当にたくさん決めることがあります。壁は漆喰にするのか、珪藻土にするのか、壁紙にするのか。ドアや取手の色や形、洗面やキッチンはどれくらいの高さが使いやすいのかなどなど。だからこそ、自分たちの生活スタイルや好みを分かってくれる担当者に出会えるかどうかが重要です。話しやすさ、連絡のしやすさ、提案力、安心感など、各社の窓口となる人との相性の見極めましょう。 工務店選びに困ったら、希望に合う会社がわかる無料相談所「ナラタテ」 家づくりを始めるときや工務店選びに困ったときは、住宅会社相談カウンター「ナラタテ」をご利用ください。奈良の住宅雑誌に携わっている編集部だからこそわかること、知っていることをお伝えするために運営しています。希望される家づくりをかなえてくれる工務店のご紹介のほか、工務店の選び方、建売住宅×注文住宅どちらが良いのか、ハウスメーカーと工務店の違い、思い描いている家づくりができる住宅会社はどこなのかといった疑問も解決できます。土地探し・資金計画・家づくりの段取りを整理し、工務店を決める前に気軽にお越しいただける、地域密着の家づくり相談カウンターです。 ナラタテ奈良店:奈良県奈良市三条大路1-7-12 ナラタテ生駒店:奈良県生駒市小明町446-1 ナラタテ押熊店:奈良県奈良市山陵町1459-3 ナラタテ3店舗共通 営業時間9:00~18:00(時間外もご相談ください) フリーダイヤル 0120-879-912 駐車場あり、お子様連れOK、完全予約制 https://nara-tate.jp/ まとめ 注文住宅なら家ができるまで半年~1年、リフォームでも最短1日~数か月といった時間が必要になります。毎日の暮らしをいかに快適にできるか、理想の住まいを実現できるか。自分たちの暮らし方や好みを理解して、住まいに反映してくれる工務店選びはとても重要です。焦らずじっくり、時間をかけて、足を運んで、最高の1社と出会えますように!
-

2025/08/14
おうち時間を楽しむアイデア〜成長に合わせた間取りと快適空間づくり〜
「家が一番ほっとする場所」──そんな理想の言葉を聞くと心底憧れます。でも正直、私の場合は、独身が長かったり地元から離れているせいか、子どもや家族との時間の過ごし方に戸惑うことが多いんです。特に夏休みのような長期休暇は、「今日は何をしよう?」「どこか行く場所ないかな?」とついネガティブに考えてしまいがち。でも、そんな悩みも、住まいの間取りや空間の工夫次第でぐっとラクに、そして楽しく過ごせることがわかりました。家族みんなが自然と集まって笑顔になれる、そんな家づくりのポイントをこれからご紹介します。忙しい毎日でも、ママも一緒にほっと一息つける「おうち時間」を一緒に楽しみましょう! 【乳幼児期】見守れる・安全・楽しいがポイント この時期は、家の中が子どもにとっての遊び場であり学びの場。毎日が小さな冒険の連続です。だからこそ、親がそばで見守れる安心感と、安全に過ごせる空間づくりが大事なポイントとなります。 ▽見通しのいいリビング 家事をしながら子どもの様子を見守ることができる、キッチンとリビングをつなげたオープンな間取りがおすすめ。リビングの一角に、絵本やおもちゃをまとめた「キッズスペース」があると、遊び場がはっきりして片付けもラクに。 ▽角は丸く、床はやわらかくする 転倒時のケガの予防として、家具の角を丸くしたり、クッションマットを敷いたりして対策する。こうした小さな安心が、親にとって大きな安心につながります。 ▽親子で楽しめる“作業コーナー” キッチン横にちょっとしたカウンターを作って、お絵描きやおやつづくりを一緒に楽しむのもいいですよね。自然に会話が生まれて、「楽しい記憶の積み重ね」ができます。 【思春期】自分の時間と家族との時間、ポイントは「ちょうどいい距離感」 少しずつ自立し始める思春期。プライバシーを尊重しながらも、自然と顔を合わせて会話できるような「ちょうどいい距離感」がこの難しい時期を乗り越えるコツです。 ▽子ども部屋は“自分らしさ”を大切に 「自分の世界」を持てる部屋づくりを実現するために、集中できるデスクや、趣味のものを飾れる棚などがあるとベストです。音や照明の快適さに配慮することで、より心地よく過ごせる空間になります。 ▽リビングを“心のハブ”に テレビやゲームだけじゃなく、ボードゲームや読書もできるような多目的スペースに。ソファやテーブルの配置を工夫して、自然と顔を合わせられるレイアウトにしてみましょう。 ▽話しかけやすい“ゆるやかスペース”を リビングの一角に小さなテーブルやカウンターを設けて、親子でちょっとおしゃべりできる場所を作るのもおすすめ。無理に会話をしなくても、距離を縮めるきっかけになります。 【子どもが巣立ったら】夫婦の時間をもっと楽しめる空間へ 子育てがひと段落したら、暮らしも次のステージへ。これからの暮らしに合わせて、空間も少しずつ変えていきましょう。 ▽空いた子ども部屋を“趣味空間”に 空いたお部屋を趣味のアトリエや書斎、リラックスできるスペースとして活用。夫婦それぞれの時間を楽しむのもよし、共通の趣味に使うのも素敵です。 ▽リビングをとっておきのくつろぎ空間に お気に入りのソファや照明を取り入れて、リビングを一番心地いい場所に。友人を呼んでのホームパーティや、家族が帰省したときの集まりにもぴったりの空間になります。 家族みんなが「心地よく」過ごすために ライフステージを問わず、くつろげる家には共通する工夫があります。 色合い:ベージュやグレー、パステルなど落ち着きのある色で統一 照明:間接照明や調光機能で、時間帯や気分に合わせて調整 素材感:木や布など、あたたかみのある素材 収納:出しやすく片付けやすいストレスフリーな収納 観葉植物:グリーンを取り入れて、やさしさと癒しを感じる空間に リビングは「家族の真ん中」にする 家族みんなが自然と集まるリビングは、日常の中の“ほっこり空間”。特別なことがなくても、会話や笑顔が生まれる場所にしていきたいですね。 ちょうどいい広さ:必要以上に広くなくてOK。全員が心地よく過ごせる広さを 家具配置:顔を合わせやすいようにレイアウトを工夫 多目的性:読書、ゲーム、団らん…いろんな楽しみ方ができるように 思い出の共有:写真や子どもの作品を飾って、会話のきっかけに まとめ おうち時間を楽しむには、「今の暮らしに合った空間づくり」がとても大切です。 乳幼児期は「安心して遊べる空間」、思春期は「自分の時間を大切にできる空間」、そして子どもが巣立ったあとは「夫婦が心地よく過ごせる空間」へ――。暮らしとともに、住まいも少しずつ育てていけるといいですよね。家族との時間が、プレッシャーではなく“楽しみ”になるように。できるところから少しずつ、あなたらしい家族のカタチを育てていきましょう。
-

2025/08/07
施工例の写真検索が便利!キッチン・風呂・洗面など16箇所、見たい部分が一気見できるっ
2025年6月に、より使いやすく、情報が探しやすくリニューアルした当サイト「奈良すまい図鑑WEB」。 奈良で実績を積んでいる優良な工務店が探せるサイトとして、新築・リフォーム&リノベーションの施工例、住まいの特集、各社のイベント情報など、「奈良で家を建てたい」「購入した中古戸建をキレイにしたい」「実家をリフォームしたい」といった思いに寄り添えるように日々情報を発信しています。 今回は、リニューアルで新しく増えた機能についてご紹介します! それが新築およびリフォーム施工例ページの「写真から探す」です。 【生駒郡・パーシモンホーム by株式会社日都建設】新築施工例のキッチン、詳しい施工例情報はこちらから 新築・リフォーム&リノベーションどちらも使える「写真から探す」 住まいづくりやリフォームを考えたとき、まず行うのが情報収集。 その際にぜひ活用していただきたいのが、「写真から探す」の機能です。 →まずは、TOPページもしくはメニューから「新築施工例」もしくは「リフォーム施工例」をクリック。 →緑色の四角「写真から探す」をクリック。 →写真キーワードが表示されるので、気になる箇所をクリック。 →選んだキーワードに該当する写真一覧が表示されます。 写真をクリックすると、そのお家の他写真や紹介文章が表示されます。 知りたいが見つかる、写真キーワード 写真検索機能で選べる写真キーワードは、次の16個。 外観、ダイニング、リビング、キッチン、階段、和室、造作家具・建具、廊下、洗面・風呂、子ども部屋、書斎、玄関、トイレ、洋室、屋外空間、扉 知りたい場所、気になるキーワードを選んで、写真表示ができます。 毎日過ごす時間が長いキッチン、住まいの顔となる玄関など、お家によってテイストはさまざま。スッキリとシンプルなお家もあれば、和風テイストのお家もあって、同じ空間がないのが面白いところ。 それぞれの住まい手の思いに寄り添い、希望をかなえてきた工務店のお家ならではです。 写真検索は、新築・リフォーム&リノベーション相互利用がおすすめ。 「奈良すまい図鑑WEB」には、新築施工例、リフォーム施工例のページがあり、それぞれで登録されている写真は異なります。「うちは新築だから」「今考えているのはリフォームだから」といった目的は違っても、完成する空間は同じです。新たなヒントが見つかる可能性もあるので、新築の場合でもリフォーム施工例のページで写真検索を。また、リフォームの場合でも新築施工例の写真検索をぜひ利用して、参考にしてください。 工務店選びの参考にもなる写真検索 Instagramやpinterest、Tumblrなど、SNSではさまざまな情報があり、検索すればするほどたくさんの関連写真が出てきます。しかし、その理想の空間を実現しているのは、奈良からは遠い会社だった。。。ということも多いはず。家の外観やキッチンなど「好きな空間」を集める方法としてSNSはバッチリ向いていますが、工事を依頼する際はまた別の検索が必要になります。「奈良すまい図鑑WEB」なら、気になった写真=実現してくれる奈良の工務店が直結。問い合わせ先やイベント情報も載っているので、その会社のことを深く知ることができます。 写真検索でイメージを膨らませて、第三者に伝えるカードを持つ。 住まいに関する「こうしたい」「こんなテイストが好き」といった参考写真があると、第三者に伝えやすく、家づくりやリフォームがとてもスムーズに進みます。「奈良すまい図鑑WEB」で掲載されているのは、確かな技術力と柔軟な対応で思いをかなえてくれる工務店です。工事を請け負う側も百聞は一見に如かずで、写真があるとわかりやすいし、好みのテイストを共有しやすいそう。 それに、いいなーと思う写真を見ているだけも楽しいし、不思議と気持ちも上がりますよね。 まとめ 住まいの新築やリフォーム&リノベーションを成功させるカギは、事前の情報収集です。理想の住まいに近い写真や雰囲気がわかる資料など、工務店担当者に伝えるカードはたくさん集めていきましょう。写真検索で写真を見ていたら、気になる写真はいつも○○工務店の施工例だったということもあるはず。施工例の「写真から探す」は、パソコンからでもスマホからでも使える機能なので、ぜひご利用ください。
-

2025/07/31
【施工写真アリ】トイレのリフォーム、まるごと?おしゃれに?とにかく快適に!!奈良県工務店リフォーム例
毎日の生活でよく使うからこそ不具合が起こりやすいのは、やはりキッチン・トイレ・風呂といった水回り。特にトイレは、家族はもちろんお客様も使う場所だからこそ、キレイに整えておきたい場所。 新しい商業施設やレストランに行くと、「フォルムがすっきりとしたトイレだー、なんてきれいで多機能なのだろう」と思う最新のトイレに出会うことはありませんか? そのトイレ、リフォームで叶います。自宅に実現できます。 「まぁ今のトイレでも不便ないし、使えているし」というのが現状かもしれません。本当によくできたもので陶器製の便器は、とても長寿命。ひび割れなどがなければ、100年は使えるといわれています。ただ、タンク内部の部品や配管の劣化、ウォシュレットや消臭機能の異音・故障などはいつ訪れるかわかりません。最近よくつまるようになった、水漏れがするようになった、という場合も交換のタイミングかも。 また、中古住宅を購入した場合、せめて水回りは新しくしたいですよね。地道にお掃除するよりも、全部取っ払って新しくしたい!と思う方も多いはず。 そこで、どんなトイレリフォームができるのかを見ていきましょう! 設備をまるごとor部分的に入れ替える 便器をごっそりまるごと交換するほか、温水洗浄機能が付いた便座部分のみ交換するなど、今お使いの便器によってできるリフォームは異なります。 トイレの種類や機能は、TOTOやLIXILなどの大手メーカーを筆頭にたくさんのラインアップがあります。機能も充実しており、汚れにくい、お手入れがしやすいといった清掃性の向上。毎日使うからこそ消臭機能が優れているといった点も重視したいところ。また、トイレ本体から音楽が流れるなど、気の利いた機能が搭載されているものも。 最近の新築では、スッキリとした見た目と節水効果が高いタンクレストイレが主流です。さらに床から浮いた形のトイレも床掃除のしやすさから採用されているご家庭も増えています。また、お家の雰囲気に合わせてトイレにもこだわり、真っ黒なトイレを採用されているご家庭も。トイレ空間の中心となる便器の色が選べるのは、こだわりの空間を実現させる上で重要なポイントかもしれません。 床から浮いたトイレ【大和郡山市・スペースマイン】施工例、同邸宅の他の写真を見る 黒いトイレ【天理市・リビングデザイン】施工例、同邸宅の他の写真を見る 壁紙や床材など空間を一新 せっかく便器を入れ替えるなら、この際、古くなった壁紙や床材を張り替えるのもオススメです。トイレの嫌な臭いは、汚れや菌の染み付きが原因の1つとも言われます。空間全体を一新することで、清々しいトイレになりますよ。 壁材としては、漆喰や珪藻土といった自然由来の素材を用いれば、調湿・消臭効果が期待できます。 壁紙にも調湿・消臭効果のあるものがあるほか、色柄は無限大。壁の一部の面だけ、お気に入りの柄の壁紙を採用するなど、遊び心を反映しやすい場所でもあります。 飛び散りが予想される部分には、メラミン化粧板なら清掃性が高くお手入れ簡単です。 床には、お手入れがしやすいビニールクロスのほか、天然大理石を使用するといったゴージャスなトイレも。天然の大理石を使っても、小さな空間だからこそコストが抑えられるそう。 また、お家の間取りによっては、扉を引き戸にして段差をなくす。ペットのトイレスペースも一緒に設けるといったリフォームも可能です。 タイル壁やヤカン型の水栓など、ご夫婦の遊び心が反映されている【明日香村・島田工務店】施工例、同邸宅の他の写真を見る 一部の壁紙をミントブルーに変えたトイレリフォーム【奈良市・ビーライフ】施工例 温熱環境を整える 扉を閉めていることが多く、窓が無いもしくは小さいといった密閉性の高さから夏はムンッと熱気がこもっていたり、冬は他の部屋よりもさらに寒く感じたり、外気の影響を受けやすいトイレ。 夏の暑さ対策には、人感センサーや湿度センサー付きの換気扇を付けるといったことも効果的です。 冬の寒さは、日中の日照不足や窓からの冷気の侵入による影響が大きいことが考えられます。ヒートショックを防ぐためにも、断熱効果が高い窓に入れ替える、壁床などに断熱材を敷くなど、温熱環境の見直してみてはいかがでしょうか。 とはいえ、そこまで予算がない!という現実もあるはず。 夏場は、窓や扉を開けて換気する、扇風機を設置するなど、空気の入れ替えができると少しはマシに使えます。 冬場は、窓にカーテンを付けたり、100均でプラスチック段ボールなどを調達して内窓をDIYすると、良いかもしれません。 トイレ施工事例 住まいづくりのプロである工務店に頼めば、いつものトイレがあっという間に一新できます。トイレリフォームの参考にしてくださいね。 信楽まで探しに行った手洗い鉢。毎日使う場所だからこそ心地よく高級旅館のような風情あるトイレ。【葛城市・建築工房和】同邸宅の他の写真を見る マンションのトイレリフォーム。玄関と同じデザインクロスを効果的に使うことで、より一層ラグジュアリーな仕上がりに。【奈良市・ビーライフ】同邸宅の他の写真を見る シンプルで洗練された印象の空間。洗面スペースとトイレをゆるやかに仕切って配置。【生駒市・ROKA architecture. by VENDOR株式会社】同邸宅の他の写真を見る 2階の床は、節ありの杉の無垢材を使用。廊下との段差を無くし、入口はドアから上吊りの引き戸へと変更した。【大和郡山市・輪和建設】同邸宅の他の写真を見る トイレには本棚を設置。壁にはにおいを吸収するエコカラットが貼られている。【五條市・HAUSQA(株式会社 平和技建)】同邸宅の他の写真を見る 洗面スペースと空間を共にしたモデルハウスのトイレ【奈良市・吉川住研】モデルハウスの情報を見る まとめ 毎日使う場所だから、新しいトイレ空間は、気分も上げてくれるはず。「こまめに掃除しよう」といった新しい習慣が身につくかもしれません。部分的な小さなリフォームから大きなリノベーションまで手掛ける奈良の工務店に、ぜひ相談してください。 →奈良県にある工務店一覧ページを見る
-

2025/07/10
ドラマの部屋に暮らしたい。中古住宅+リノベで叶える、あの世界観と理想の暮らし。
「新築じゃなくて、中古住宅を買ってリノベーションという手もあるのか。」 そう思うようになったきっかけを思い返すと、やはりドラマの影響が大きかった気がします。 たとえば『続・続 最後から二番目の恋』。鎌倉の古民家で繰り広げられる、ちょっと切なくて心地よい大人の物語。その舞台となる家の美しさに、何度もため息をついたものです。年月を重ねた木の風合い、風の通る縁側、和と北欧が共存するインテリア。まさに“味わいのある暮らし”を体現していました。これはハマりすぎて、コロナ禍に入る前の2019年だったかな?気付くと聖地巡礼で、極楽寺駅に降り立って写真を撮っていました(笑)。 『モテキ』では、長澤まさみ演じる松尾みゆきの住むヴィンテージマンションが印象的でした。築年数のあるマンションの一室を、素敵すぎるキッチンを中心として、アートや照明、小物で個性的に彩った空間。天井の高さや古い建具もそのままに、自分らしい暮らしを楽しむ姿に心が惹かれました。 そして『大豆田とわ子と三人の元夫』。松たか子演じるとわ子の部屋は、シンプルでありながら素材感や余白にこだわった、とても美しく洗練されたリノベ空間。自然光、木のぬくもり、整った収納――“心地よい日常”ってこういうことかもしれないと、憧れを抱かずにはいられませんでした。見るたびにいつも、「ああ、この世界観に入りたい」と思うのですが、それは、リノベされた空間とインテリアの醸し出す部分が大きいように思います。という事は、私たちは、リノベーションによってあの世界観に没入し、生活できるってことですよね?なんて夢のある話なのでしょうか? その物件、本当にリノベ向き?最初に見るべき4つのポイント リノベーションを成功に導くためには、8割が物件選びで決まるといわれるほど重要。価格や立地だけでなく、「この建物は本当にリノベに向いているのか?」という視点が大切です。 「輪和建設」リノベーション施工事例、詳細ページを表示。 1.築年数と耐震性 1981年6月以前の建物は旧耐震基準のため、安全基準を満たしていない可能性があります。 リノベ費用に耐震補強の予算が必要になることもあるので要注意。 2.間取り変更のしやすさ 木造軸組工法は、壁を取り外して間取りを大きく変えやすいです。でも、ツーバイフォー工法やRC造は、壁が建物の大事な柱の役割をしているので、間取りを変えるのが難しくなります。 3.法的制限と「再建築不可」問題 再建築不可の土地は、建て替えや売却時に大きな支障が出る可能性があります。 購入前に必ず法的制限の確認を行い、不動産会社や役所にチェックしてもらいましょう。 確認しておきたい主な法的制限 ・接道義務:幅4m以上の道路に2m以上接している必要あり ・用途地域・建ぺい率・容積率:建物の種類・大きさが制限される ・高さ制限・斜線制限:周囲への日照や景観に配慮した高さの制限 ・防火地域:建物の構造や設備に制限あり ・特別規制(文化財・風致地区など):外観・用途に制限がかかることも ・宅地造成等規制法:造成地では安全対策や許可が必要な場合あり 4.インスペクション(建物診断)を行う 見た目はきれいでも、中の配管や基礎に問題を抱えていることもあります。専門家による調査で、雨漏り・シロアリ・劣化などのリスクを事前に見つけることがとても重要です。 中古住宅リノベのメリット&デメリット 「安い」だけじゃない、中古リノベの本当の魅力。 「ROKA architecture. by VENDOR株式会社」リノベーション施工事例、詳細ページを表示。 メリット ●新築よりも割安 物件価格は新築の約3〜4割安く、その分をデザインや機能のグレードアップに使えます。 ●立地で妥協しない 駅近や人気エリアでも、中古なら選択肢が広がり、理想の場所に住める可能性が高まります。 ●資産価値の下落がゆるやか 築10年以上の物件は、価格の下落がある程度落ち着いているため、資産価値が安定しやすい傾向があります。 ●デザイン自由度が高い スケルトンリノベーションなら、内装や間取りを一から自由に設計可能。理想の空間づくりができます。 ●補助金や税制優遇の対象になることも 耐震改修や省エネリフォームなど、条件によっては補助対象になることも。 ●周辺の情報を事前に把握できる ある程度、まわりにどんな人が住んでいるのかを知ってから入居できる。 ●安定した住環境を確保できる まわりに空き地などがなければ、全部屋の日当たり、窓からの景色や住環境が大きく変わることがない。 デメリット ●傾きや老朽化のリスク 一部の部屋や家全体に傾きがないかを事前に確認することが重要です。また、配管や配線、屋根などが古い場合、予想外の追加費用が発生することもあります。 ●保証が限定的 中古物件は、構造躯体の保証、雨漏りなどの防水に関する保証、設備の保証について、長期保証がないか、短期間の保証しか付かない場合が多いです。 ●工事中の仮住まいが必要 フルリノベーションには3〜6ヶ月かかるため、その間の仮住まいや引越し費用も考慮しましょう。 ●ローン審査が厳しいことも 中古物件は担保評価が低く、住宅ローンの条件が厳しくなる場合があります。ただし、「中古+リノベ一体型ローン」などの選択肢も増えています。 快適に暮らすためのリノベ3大ポイント 見た目だけでなく、日々の暮らしを快適にする工夫も見直しましょう。 「吉川住研」リノベーション施工事例、詳細ページを表示。 1.耐震補強 構造の安全性は命を守る最優先事項。基礎や壁の補強、構造金物の追加など、専門家の診断を踏まえた設計を。 2.断熱性能の向上 築古物件は断熱性能が不十分なケースが多く、快適性と光熱費に大きく関わります。床・壁・天井、そして窓も断熱仕様に。 3.設備の刷新 給排水管や電気配線の老朽化はトラブルの元。リノベ時に一新しておくことで、長く安心して暮らせる基盤が整います。 まとめ 「ビーライフ」リノベーション施工事例、詳細ページを表示。 『続・続 最後から二番目の恋』や『大豆田とわ子』のような暮らしは、ドラマの中だけの話ではありません。中古住宅+リノベという選択肢によって、思い描いた通りの空間は自由に一から作ることができます。 理想の家づくりへの第一歩は、物件の状態、法的条件、将来を見据えた設計。そして、そのための入念な下調べと準備。それらをひとつひとつ丁寧にクリアしていくことです。 「“らしさ”にこだわる。自分だけの空間で暮らす毎日。」 「好きに囲まれて、自分らしく暮らす。」 その想いを、現実のものに。 “ここで暮らしたい”と思える場所が、中古住宅の中にきっと見つかります。
-

2025/07/03
二世帯住宅という選択肢!暮らし方の基本を知ろう
「3つの型」と「間取りで配慮するポイント」とは? 実家が遠い私にとって、二世帯住宅という選択肢 子育てに追われる毎日の中で、「もし親が近くにいてくれたら」と感じたことはありませんか? 私自身、県外出身で実家は遠方。頼れる家族が近くにいない状況で、育児や家事を夫婦だけでこなすのは本当に大変です。加えて、自身の体調にも変化が訪れる“プレ更年期”の時期に差しかかると、心身ともに疲れがたまりやすくなり、将来への不安も増してきます。そんなときにふと思い浮かぶのが「二世帯住宅」という選択肢。 親と同居することで、子育てや家事のサポートを得られる安心感は大きな魅力です。また、介護に対するハードルも下がります。ただし、生活リズムの違いやプライバシーの確保など、気になる点も多いのが現実。だからこそ、間取りや住まい方に工夫を凝らせば、無理なく支え合える“ちょうどいい距離感”をつくることが可能になります。 本記事では、そんな“子育て+更年期世代”にこそ知ってほしい、二世帯住宅の3つのタイプと、それぞれの暮らしに合った間取りの工夫について、わかりやすくご紹介します。 二世帯住宅とは?3つの型を理解しよう 二世帯住宅は、親世帯と子世帯が同じ建物内で生活する住宅です。生活スペースや設備の「共有の程度」によって、以下の3つの型に分けられます。 1.完全分離型 玄関・キッチン・浴室・トイレ・LDKなどすべてを別々に設けるタイプ。それぞれの世帯が独立して暮らせます。 メリット デメリット ・プライバシーをしっかり確保できる ・万が一空き家になっても賃貸活用が可能 ・緊急時にはすぐ助け合える距離感 ・建築費用が高くなりやすい ・広めの土地が必要 ・意識しないと顔を合わせる機会が減る可能性も 2.部分共用型 玄関や浴室など一部を共用し、他の空間は分けて生活するスタイル。独立性と共有のバランスを図れます。 メリット デメリット ・程よい距離感を保てる ・完全分離よりコストを抑えやすい ・階を分けるなどの工夫で生活リズムの違いにも対応しやすい ・共用部分ではプライバシーの配慮が必要 ・光熱費などの費用分担が曖昧になりがち 3. 完全同居型 玄関・キッチン・リビングなど、すべてを共用するスタイル。寝室のみを分けることが多いです。 メリット デメリット ・生活に必要な設備が1セットで済むため費用を抑えられる ・介護や育児で協力しやすい ・一世帯になっても違和感なく暮らせる ・プライバシーがほぼない ・生活リズムの違いによるストレスが出やすい ・お互いの夫婦喧嘩が筒抜け ・音やにおいの干渉に配慮が必要 間取りで失敗しない3つのポイント 実際の設計では、和室と洋室をうまく使い分けたり、1階を親世帯、2階を子世帯にしたりする工夫が効果的です。部分共用型では、玄関だけを共用し、水回りやLDKを別にすることで快適性が向上。音やにおいの干渉も抑えられます。間取りの工夫で快適な二世帯生活を実現しましょう。 1.プライバシーを守る設計 家族といえども、プライベートな空間は必要です。遮音性のある壁や、親世帯の寝室と、子世帯の寝室、さらに、水回りを遠ざける配置でストレスを軽減できます。 2.ライフスタイルの理解と調整 世帯ごとの生活リズムや趣味の違いをあらかじめ把握しておくことが大切。例えば、親世帯が早寝早起きで、子世帯が夜型の場合は、上下階で空間を分けるのがおすすめです。 3.家事・費用のルールを明確に 光熱費や日々の家事を分担する場合は、「共通口座を作る」「費目別に分担する」などのルールを事前に決めておくことで、トラブルの防止につながります。 迷った場合の解決策!いったいどのタイプの二世帯住宅が合うのか 二世帯住宅は「誰と」「どう暮らしたいか」が明確になるほど、快適で心地よい住まいになります。完全分離・部分共有・完全同居も、メリットデメリットはそれぞれ。迷った場合のおすすめは、一度どちらかの家で、完全同居して暮らしてみること。少なくとも1ヶ月。できれば3ヵ月。たまに顔を合わせる程度だと見えない…お互いの生活が見えてきます。将来を見据えた安心の暮らしのために、自分たちに合ったスタイルを見つけてください。 まとめ:二世帯住宅は“暮らし方”に合わせた選択を 二世帯住宅は、子育てや介護といったライフステージの課題に対して、心強いサポートを得られる住まい方です。しかし、親子とはいえ生活リズムや価値観の違いは避けられないもの。だからこそ「どんな距離感で暮らしたいのか」を家族でしっかり話し合い、それに合った住宅の「型」と「間取り」を選ぶことが何より大切です。 完全分離型:生活スタイルが異なる世帯に◎ → それぞれが独立して暮らせるから、プライバシーも安心 部分共用型:程よい距離感とコストのバランスを求める家庭に◎ → 一部を共有しながら、個々の空間も確保できる 完全同居型:協力しながらの子育て・介護を重視する家庭に◎ → 一緒に支え合う安心感があり、家族のつながりも深まる 家族みんなが笑顔で過ごせる住まいづくりを、今こそ一緒に考えてみましょう。 ライター 内藤美由紀
-

2025/06/27
空き巣を寄せ付けない!安全な暮らしを実現するための防犯の新常識とは?
〜最新グッズ・間取りの工夫・住宅設備の視点から〜 「え?鍵閉めたっけ?」 いつもそう思って玄関に戻って確認してしまう——。 私は元来、そんなタイプの人間です。鍵をかけた記憶が曖昧なとき、ちょっとした不安が心をよぎる。けれど、心のどこかで「まあ、鍵さえかかっていればマンションだから大丈夫だろう」と、防犯に甘い意識で日々を過ごしているという人もいるのではないでしょうか。私もその一人でした。 しかし、これが戸建てとなれば話は別。 もしも将来、家を建てるとしたら、防犯対策はしっかりと講じておきたい。 鍵のかけ忘れが気になってしまう私のようなタイプでも、安心して暮らせる最新設備や、防犯性を高める間取りの工夫があるのではないかといろいろと調べ取り入れました。 そこで今回は、「狙われにくく、侵入されにくく、万が一にもしっかり備える」ための防犯対策について、最新グッズや住宅設備、間取りの工夫など、住まいづくりに役立つ視点からご紹介します。 テクノロジーで守る家~最新防犯グッズの活用法~ 防犯対策の第一歩は、日々進化を遂げている最新の防犯グッズを導入することです。とくに近年は、ただ備えるだけでなく、防犯設備の存在を可視化する「見せる防犯」が有効であると言われています。 ・スマート防犯カメラ AIが人間の動きや表情を瞬時に察知し、不自然な動きがあるとスマートフォンにすぐにお知らせ。「見せる防犯で空き巣に狙われにくくし、仮に侵入されてしまった場合は証拠が記録される」夜間の暗視機能や、不審な来訪者にリアルタイムでスマホ越しに声を掛けられる双方向通話なども搭載。留守中に自宅の様子をチェックできる安心感があります。 ・スマートロック(電子錠) 施錠に不安を感じやすく、出先でモヤモヤしてしまう方(←まさに私みたいなタイプ)にとりわけおすすめ。外出先から施錠確認・操作ができるほか、指紋や顔認証機能付きなら鍵を持たずに外出できます。仮に施錠し忘れていたとしても、スマートフォンに通知が届くので安心です。 ・人感センサー付きLEDライト 人の気配を感知して自動でライトが点灯。 「狙わせない」空間づくりにひと役買います。録画・警告音機能付きの先進モデルも増えており、手軽に設置できる防犯アイテムとして人気が高まっています。 ・GPS付き防犯ブザー 子どもや高齢者の遠隔サポートには、防犯ブザーにGPSが搭載されたものが安心。居場所を知らせる通知が保護者へ瞬時に届くため、安心して見守ることができ、緊急時にも素早い対応が可能です。 間取りの工夫で「侵入を防ぐ安全な住まいに」 防犯性を高めた住まいづくりは、実は間取りの工夫でも実現します。住宅設計の段階で意識するだけで、おのずと空き巣にとって“侵入しにくい家”が完成します。 ・死角をなくす 敷地内の死角は不審者の隠れ場所になってしまいます。植栽や外構を工夫して見通しを良くし、裏口周辺は照明やカメラでしっかりと対策しましょう。 ・玄関や窓の設置場所や防犯対策 玄関は可能な限り通行人の目につきやすい場所に。裏手や人目につかない位置にある窓には、防犯ガラスや格子を併用することで安全性が高まります。 ・セキュリティーゾーンの考え方 玄関から直通でリビングに入る間取りでは、万が一侵入された際に危険度が高まります。玄関から生活空間までにセキュリティーの一層として、廊下や扉を設けることで、感覚的にも機能的にも侵入を防ぐ構造が作れます。 住宅設備の工夫で「家族の安全を守る住まいへ」 暮らしにさりげなく防犯対策を溶け込ませるには、設備そのものが防犯対策になるように設計するのがベストです。スタイリッシュな防犯カメラや、デザインにこだわった防犯シャッターなど、防犯性とともに、デザイン性や快適性を兼ね備えた住宅設備が増えてきています。 ・防犯合わせガラス 2枚のガラスの間に強靭なフィルムを挟んだ防犯ガラスは、割れにくく、破片も飛び散りにくいため、侵入を大幅に遅らせることができます。 ・録画機能付きインターホン 来訪者を録画・記録できるインターホンは、不在時の訪問も確認でき、ストーカーや押し売り対策にも。スマホと連携すれば、外出中でも応対が可能です。 ・電動シャッターやスマート雨戸 スマート雨戸は、IoT技術を活用し、自動開閉やスマホ操作ができる新しいタイプの雨戸です。天候センサーやタイマー機能によって自動で開閉し、スマートホーム(家電や設備をネットにつなぎ、自動化・遠隔操作ができる家)と連携することで、より快適で便利な暮らしを実現します。タイマー機能付きなら、不在時も在宅を装えて防犯や省エネに効果的。操作の手間も減り、日々の暮らしがより快適になります。 ・ホームセキュリティーシステム スマートホームと連携することで、より高度な防犯や自動化が可能になります。たとえば「玄関の鍵が開いたらライトとカメラが自動で作動する」など、暮らしに合わせた設定ができます。さらに、警備会社と連携したシステムであれば、侵入対策だけでなく、火災やガス漏れといったリスクにも対応可能です。 異常を感知すると、センサーがすぐに反応し、スマホや警備会社へ通知。契約プランや機器によって通知方法は異なりますが、状況に応じて警備員が現場へ駆けつけるので安心です。 まとめ:防犯は「心穏やかな暮らしへの先行投資」 防犯対策は、「いざという時のためだけの対策」ではなく、実は、毎日の安心を支える暮らしの基盤です。自分や家族が心穏やかな暮らしを送るために、最新技術を搭載した防犯グッズや設備を利用して、設計段階から防犯を意識した家づくりを進めることは、未来の安心への投資とも言えるでしょう。 これから家づくりをする方も、今の住まいに少しでも不安がある方も、ぜひ一度「自宅の防犯対策」を見直してみませんか? “カギ、ちゃんと閉めたかな?”と不安になるあなたにこそ、必要な防犯対策がきっとあります。 ライター 内藤美由紀
-

2025/06/20
「趣味を楽しむ」ための家づくり
注文住宅を建てる醍醐味のひとつに、「趣味を楽しむ空間をつくれること」があります。これは、間取りも使い方も自由に決められる注文住宅ならではの魅力です。 とはいえ、実は私にはこれといった趣味がありません。これまで何度も趣味を見つけようとしたものの、なかなか長続きせず、気づけば次のことへ……。これははまれると思って、追っていたKPOPアイドルにですら、3ヵ月過ぎた頃に瞬時に冷めたときは、さすがに自分でもがっかりしました。でも、そんな私にも「好きなもの」や「好きな雰囲気」はしっかりあって、それに対してのこだわりは意外と強かったりします。もしかすると、それも立派な“趣味”の一種なのかもしれません。家づくりでは、「好きな場所」や「趣味を楽しむ空間」をつくることが、自分らしい暮らしへの大きなヒントになります。家は「住む場所」であると同時に、「人生を楽しむ場所」。趣味がなくても、好きな雰囲気やこだわりがあれば、それを生かす空間づくりはきっと可能です。今回は、趣味や世界観を取り入れた工務店の家づくりの実例とアイデアをご紹介します。 趣味スペースは「贅沢」ではなく「必要」 以前は趣味のための空間は、限られたスペースの中で後回しにされがちでした。しかし、在宅時間が増えた現在では、自分だけの時間を過ごす場所として「趣味の空間」が暮らしに欠かせない大切な場所となっています。音楽や読書、ガーデニングなど、それぞれの「好き」を家の中にどう取り入れるかが、より快適で満足度の高い住まいづくりの重要なポイントとなっているのです。 ヨシダデザイン工房(大和郡山市)施工事例 車やバイクにこだわりがある方には、専用のガレージスペースの設置をおすすめします。雨風をしのげるだけでなく、メンテナンスやカスタマイズが快適に行える場所があると、趣味の時間がより充実します。また、こちらのガレージ内のペイントやサイン看板などは、工務店がオリジナルで造作。自分だけの特別な空間をつくることで、愛車への愛着も一層深まります。 一級建築士事務所輪和建設株式会社(大和郡山市)施工事例 リビング横に設けられた茶室は、伝統と現代が調和する落ち着いた空間。お施主様が家業とされている作業場ともゆるやかにつながり、日々に静かな癒しをもたらします。休憩室としても機能し、仕事の合間に心身を整えられる大切な場所です。 小さくてもいい、「自分だけの居場所」をつくる 趣味の空間は、一部屋まるごとでなくてもOK。階段下の本棚や窓辺の小さなデスクなど、1〜3帖のスペースでも工夫次第で居心地の良い趣味空間に。大切なのは「個室でなくても集中できる場所」をつくることです。 一級建築士事務所リビングデザイン(天理市)施工事例 LDK全体においては、和室も含め、可能な限り仕切りのないウォールレスなレイアウトを採用。天井を通常より10cm高くし、窓も天井付近まで大きく取ることで、開放感を演出しました。LDKをより広く見せる視覚的な工夫として、3帖の畳コーナーは、天井を15cm下げて間接照明を設けました。 家族と楽しむ「共有型趣味空間」 趣味は一人でも楽しいですが、家族と共有する空間づくりもおすすめ。防音スペースで音楽と読書を楽しんだり、アイランドキッチンで料理やパーティーを満喫したり。親子でDIYも楽しめます。 株式会社スペースマイン(大和郡山市)施工事例 麹の素晴らしさを伝える料理研究家である奥様がこだわり抜いた、譲れない想いが詰まったキッチン兼作業場です。造作家具にはアイアン作家の作品がアクセントとして加えられ、どこを見ても奥様の好きなものが溢れています。料理教室の開催や娘さんへの食育など、多彩な用途に対応できる、機能的で魅力あふれる素敵な空間となっています。 外とつながる「アウトドアリビング」 ウッドデッキや中庭を活用したアウトドアリビングは、自然を感じながら趣味を楽しめる人気の空間。屋根やシェードで快適性を高め、植栽やフェンスでプライバシーも確保できます。 株式会社ビーライフ一級建築士事務所(奈良市)施工事例 半屋外のオープンテラスは、外部からの視線を気にせずにプライベートを心ゆくまで堪能できます。BBQや、「エコスマートファイヤー」の暖炉など季節を問わずに楽しむことが可能。 趣味の数だけ、間取りがある 趣味に合わせて空間設計も変わります。音楽や映画は防音を、カメラや手芸は収納を工夫。趣味ごとの最適な間取りが、暮らしの快適さと満足度を高めてくれます。 HAUSQA by 株式会社 平和技建(五條市)施工事例 たくさんの本や趣味のアイテムを収納できる造作の本棚。机の天板はホワイトアッシュの幅はぎ材で上品な印象です。さまざまな趣味のスペースとして活用できます。 まとめ:趣味が暮らしを豊かにする 趣味の空間は単なる遊び場ではなく、日々の暮らしを豊かにする大切な要素です。自分の「好き」を無理なく取り入れることで、住まいはより快適で心地よい場所になります。家族構成やライフスタイルに合わせて、自分にとって心地よい“趣味との距離感”を考えることが、理想の家づくりへの第一歩となるでしょう。趣味を楽しむ空間づくりは、毎日の生活に彩りと充実感をもたらしてくれます。 ライター 内藤美由紀
-
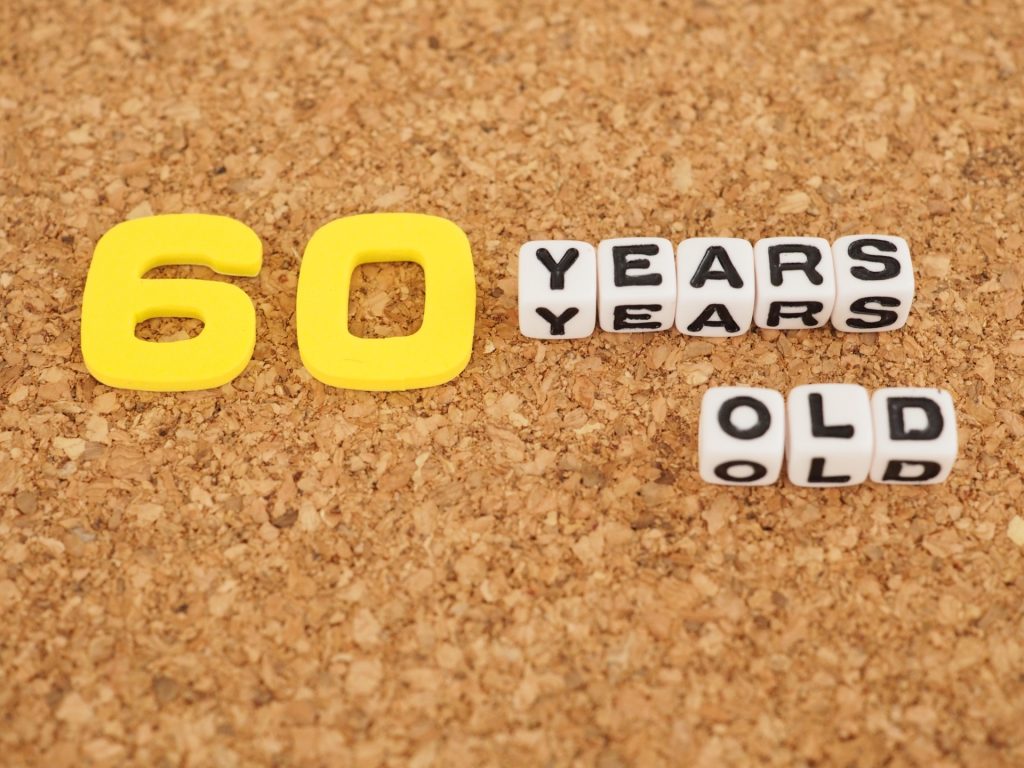
2025/06/12
60代からの家づくりの最適解とは?後悔しない家づくりの秘訣と間取りの工夫
「バリアフリー」と「ユニバーサルデザイン」を取り入れた、安心・快適な暮らし 60代からの家づくりを考える方が増えています。自然豊かな地方への移住、子世帯との同居を見据えた二世帯住宅、退職金を活用した“最後の家”づくりなど、目的は人それぞれ。たとえば、子どもの独立を機に、60代のご夫婦が2階建てから平屋へ建て替えるケースも見られます。子育てを終えたこの時期は、これからの暮らしを安心・快適に過ごすために、新築やリフォームを検討するよいタイミングです。同時に、年齢とともに現れる身体の変化に備え、「使いやすさ」と「安心」を両立した住まいづくりが求められます。 60代で新築を選ぶ方は、コンパクトな間取りや平屋住宅など、安全性と暮らしやすさを重視する傾向にあります。ただし、住宅ローンの条件が厳しくなることや、将来の介護に備えた設計として、バリアフリーやユニバーサルデザインを取り入れるなど、先を見据えた工夫が欠かせません。 今回は、「バリアフリー」と「ユニバーサルデザイン」の違いを踏まえながら、60代からの家づくりに役立つ間取りや設計のポイントを考察していきます。 ・「バリアフリー」と「ユニバーサルデザイン」ってどう違うの? 「バリアフリー」と「ユニバーサルデザイン」は、どちらも暮らしやすさを追求する考え方ですが、実は似て非なるものです。それぞれの違いを正しく理解することで、60代からの住まいづくりに最適な設計が見えてきます。 ・バリアフリーとは、困っている人のために“障壁”を取り除く 高齢者や障がい者の生活に支障が出ないよう配慮して、段差や狭さ、使いにくさといった物理的な負担を減らすことを目的とした考え方。 (例)玄関のスロープ設置、浴室の段差解消、トイレへの手すり設置など。 ・ユニバーサルデザインとは、すべての人に“やさしい空間”をつくる 年齢・性別・国籍・身体の状態に関係なく、「誰にとっても使いやすい」ことを目指す設計思想。 (例)レバー式のドアノブ、音声案内つきのエレベーター、操作しやすい自動水栓など。 どちらも欠かせない考え方であり、60代からの家づくりではその両立が理想的です。 60代からの家づくりにおける意識したい8つのポイント 介助・介護に配慮した暮らしやすい間取り 設計の工夫一つで、毎日の暮らしやすさが大きく変わります。安心・快適な住まいをつくるには、介助や介護が必要になる可能性も踏まえた設計がマストです。以下のポイントを意識することで、家族全員が、暮らしやすく、長く安心して住める空間が整います。 ①廊下は広めに確保 ・理想は幅120cm以上。最低でも90cmを確保。 ・車椅子や歩行器を利用することを想定して、余裕のある設計を。 ②段差を解消 ・転倒リスクを減らすため、玄関・浴室・トイレなどはフラットな設計に。 ・家具の配置は通りやすさを考慮し、すっきりとした空間をキープしましょう。 ③トイレ・浴室に介助スペースを ・トイレは1.2m×1.5m以上の広さが理想。(介助者が同時に入れる広さと、車椅子の回転スペースを確保するため) ・手すりの設置や、便座の高さ調整(約40〜45cm)も大切。 ・浴室はまたぎやすい浴槽、滑り止め加工、手すり設置などで安全性を確保。 ④キッチンの工夫 ・立っても座っても作業しやすい高さのカウンター。 ・少ない力でスムーズに開閉できる引き出しや収納、効率の良い動線で体への負担を軽減。 ・家族とのコミュニケーションを取りやすい対面式のキッチン。 ⑤収納は“取りやすい高さ”に ・無理な動作を避けるため、手が届きやすい腰〜目線の高さに収納をまとめて、取り出しやすさを重視。 ・可動棚なら、暮らしの変化にもフィットしやすく便利です。 ⑥ 生活動線のシンプル化 ・移動が楽になるよう、寝室・水まわり・リビングを近くにまとめる。 ⑦ドアは引き戸にする ・場所を取らずに開閉できるため、介助の際も邪魔になりません。 ⑧明るく均一な照明で、影を減らす工夫が大切 ・部屋全体が明るい照明で、視認性と安全性を高めます。 新築?それともリフォーム?選び方のポイント 新築では、「退職金を活用した最後の家づくり」として、段差のないフラットな間取りや平屋、二世帯住宅など、選ばれることが多くなっています。一方でリフォームは、今の住まいを生かしながら段差をなくしたり手すりを設置したりと、安全性を高めるバリアフリー化が大きな魅力です。 ・新築の場合 新築は最初から自由に設計できるため、バリアフリーやユニバーサルデザインを存分に取り入れられ、将来を見据えた安心の住まいづくりが可能です。 ・リフォームの場合 既存の構造を生かしつつ、段差解消や手すりの設置、引き戸への変更など、必要な部分から順に改善していくのがポイントです。予算に応じて優先順位を決め、無理なく進めましょう。 まとめ:「今の快適さ」と「将来の安心」を両立する家 60代からの家づくりは、今の暮らしを大事にしながら、将来の安心にも備えておくことが非常に重要です。「バリアフリー」と「ユニバーサルデザイン」を取り入れることで、誰もが快適に、そして安心して長く暮らせる住まいが実現します。 間取りの工夫次第で、暮らしの快適性は飛躍的に向上します。 将来への備えとして、今の暮らしをより快適にする住まいづくりを考えてみましょう。 人生の新たなステージに向けた「60代からの家づくり」が、 これからの暮らしに明かりを灯し、心豊かな日々をもたらしますように。 ライター 内藤美由紀
-
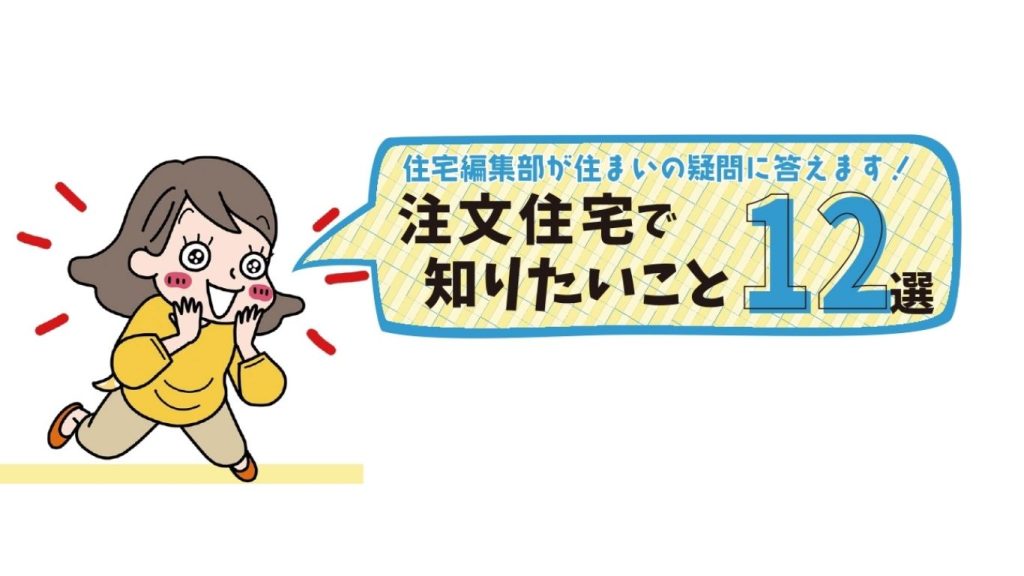
2025/06/02
【住宅編集部が答える!】注文住宅で知りたいこと 12選!!
奈良すまい図鑑編集部が取材でよく聞くエピソードや、運営する『住宅会社紹介カウンター ナラタテ』でお受けする質問をピックアップしてお答えします。不安や疑問を解消して注文住宅がますます楽しみになりますように。 1.新築における防犯対策は、どんなことができますか? ヨシダデザイン工房 空き巣の侵入方法は、窓からが圧倒的に多く、次に玄関などのドアからのようです。空き巣の大半は侵入に5分以上かかると犯行をあきらめるといわれているので、開口部の対策を強化するといいでしょう。1階部分の窓には防犯ガラスやシャッターを設置することでたやすく侵入することを妨げます。玄関などのドアにはディンプルキーの導入がおすすめです。ディンプルキーは、通常のシリンダーキーよりピッキングが難しいため侵入を妨げます。センサーライトや防犯カメラの設置も有効です。また、敷地内が見えなくなるような高い塀や生け垣は、隠れやすく空き巣に好まれる条件が整ってしまいますので、オープン外構にするのもおすすめです。プライバシーの確保も両立するには、植栽やフェンスの建て方を工夫するのもいいでしょう。 2.造作家具ってよく聞くけど、どんなものですか? スペースマイン 「造作家具」とは、間取りやスペースの広さ、収納したいもの・置きたいものに合わせて、工務店や設計事務所が一から設計・製作・施工を行う家具のことです。完全オーダーメードで、基本的に床・壁・天井などに固定します。造作家具の最大の魅力は、自由度の高さです。既存の家具や設備を置くのではなく、空間やテイストに合わせてリビングの一角にテレビボードを備え付けたり、大きなものになれば、キッチンや洗面スペースに生活スタイルに合わせた棚を作ったり、統一感がある使い勝手のいい空間を作ることができます。 3.家事をしながら子どもを見守れるキッチンにしたい。 一級建築士事務所 リビングデザイン 子どもたちが遊ぶことのできる空間をリビングやダイニングに設けてはいかがでしょうか。遊び場や勉強スペースがLDKにあると、家事をしながら子どもの様子を見ることができます。キッチンで作業している親に対して、話しかけにくいと子どもは感じる場合もあるため、オープンタイプのキッチンにするだけでコミュニケーションのハードルを下げることができます。対面や回遊性のあるカウンターキッチンを設け、料理をしながら子どもと話をしたり、子どもが大きくなってくれば手伝ってもらったりしすいレイアウトもおすすめです。LDKの中心の家事動線をコンパクトにすることで、子どもを見守りながらもゆったり、家族でくつろげる空間になるよう考え るのがポイントです。 4.子どもがまだ小さいので、先に子ども部屋を作るか悩んでいます。いい方法はありますか? 建築工房 和-nagomi- 今すぐ必要だと感じなければ変動性のある間取りを考えてみてはいかがでしょうか。子ども用のフリースペースや間仕切りのない小上がりを作り、子育て中はキッズスペースとして、成長したら客間にするなど別の用途に転用できます。個室を作るのであれば、あとから壁を設ける工事は難しくないので、まずは大きな部屋を設けておき、子どもの成長にあわせて仕切って使えるように可変性のある間取 りにするのもおすすめです。子どもが小さいうちは家族の寝室として使うこともできます。 5.家事をしやすい間取りにしたいけど、どうしたらいいかわかりません。 北条工務店 料理や洗濯、掃除など、家事のために移動する経路を「家事動線」といいます。家事をしやすくするには、この「家事動線」をコンパクトにまとめるといいでしょう。特に水回りの動線を集約し、効率的にすることで家事ストレスが軽減されます。洗面所からキッチン、リビングへの移動が一方通行ではなく、ぐるぐると回ることができる「回遊動線」にすることで行き止まりなく家事を行うことができます。また、アイロンや掃除機など、それぞれ使う場所に収納するのもひとつです。生活スタイルを考えてみて、家族の動きなどを把握することで、何がどこに必要なのかが見えてきます。 6.ハウスメーカーと工務店、設計事務所の違いを知りたいです。 ハウスメーカーって? ハウスメーカーには明確な定義があるわけではありませんが、あえて工務店や設計事務所と区別するとすれば、自社工場を持ち、規格化された一定の品質の建材や設備を大量生産することでコストを抑え、全国規模に住宅の提供を展開している会社と言えます。 仕様が統一されているので、商品の供給も安定しており、ハウスメーカーが価格やテイスト・仕様別に基本プランを作成し、その中から選ぶことができます。規格外の要望があれば、特注としてオーダーもできます。ただ特注扱いなので、コストは高くなる傾向にあります。 工務店って? 工務店の多くは地域に密着しており、土地に精通していることが多いため、建てたい土地の特長を生かした建築を得意とします。設計から施工まで建物工事の全部を請け負い、自由度の高い設計を手掛けることが大きな特長です。規格に沿ったプランを提供するハウスメーカーでは対応できない狭小地や変形地の建築にも対応できます。 工務店によって得意とする設計やデザイン、特色がありますので自分のイメージに合った工務店を探すことでオリジナリティーのある家づくりが可能になります。 設計事務所って? 設計事務所は、その名前の通りお客様の望む間取りや内観、外観をヒアリングで丁寧に拾い上げ、細部にわたり一から「理想の住まい」を設計し作り上げる会社です。設計士が在籍しており、敷地の形状や周囲の環境も踏まえ、独自性の高い唯一無二の設計プランの実現が可能となります。 主な仕事は、工務とは独立してかなえたいデザインを形にする設計です。工務店と提携している設計事務所であれば、設計完成後にそのまま設計事務所から信頼する工務店に工事依頼してくれますので、設計から完成までワンストップで行えます。 土地の形状や地盤、希望している要望に即して構造体を選ぶことができるのも魅力のひとつです。 家づくりで最も重要なことは「家づくりのパートナーをどこに決めるか」です。どんな家に住みたいか、生活スタイルなどを考え住まいのイメージを一緒にかなえてくれる住宅会社を選んでください。 7.信頼できる会社かどうかは、どう判断したらいいですか? 住宅会社紹介カウンター ナラタテ 一番いいのは、実際に工務店や住宅会社へ行って、これまでどんな家を建ててきたのか、どんなスタッフが働いているのか、よく見聞きし雰囲気を知ることです。 でも、「いきなり行くのはちょっと」という場合はそれぞれの会社が行っているイベントや見学会、注文住宅を建てた方の住まいを見ることができるOB訪問などをきっかけに、実際の施工例を巡りながら、いろんな会社と接点を持つことをおすすめします。予算も土地もなにも決まっていないし、漠然としたイメージだけしか今はないという方でもイベントなら、気軽に参加OKな雰囲気です。 それでも住宅会社に迷っていたり、家づくりに対する不安が募ったりしたときは、住宅相談窓口を利用するのもおすすめです!第三者の立場からお客様の要望を整理し、家づくりのステップを進めるための相談ができます。 8.収納力のある玄関にしたいけど、すっきりも見せたい。 マイ工務店 来客用と普段家族が使う玄関を分けたファミリー玄関というスタイルがあります。散らかりやすい玄関を分けることで、来客時に慌てることがなくなります。 扉付きのシューズクロークを設置すると、収納が丸見えになることなくすっきりとした空間を保つことができます。その扉に鏡をつけることで、身だしなみのチェックができる+空間が広く見えるという効果も! 土間収納を設けると、アウトドア用品やスーツケース、三輪車など外からそのまま収納することができます。それぞれ収納量・レイアウト・動線などが大きく異なるため、玄関の間取りや生活スタイルを考え住宅会社と相談し選ぶことが大切です。 9.毎日使うキッチンの手入れを楽にしたい!おすすめの設備はありますか? キッチンを選ぶときは、メーカーとグレードをチェックしましょう。多くのメーカーは、だいたい3種類のグレードを展開していて、それぞれデザインや対応しているオプションが違います。本当に必要な設備をしっかり想定して自分に合ったキッチンを選ぶことが大切です。今回編集部がご紹介するのはLIXILの「リシェル」です。LIXILのキッチンは、使いやすさとデザインの良さが調和しており、価格も手頃でバランスの取れたキッチンとして定評があります。「リシェル」の魅力は多種多彩。ワークトップ(天板)は、熱や傷に強く、デザイン性も高いセラミックで作られ、熱いままのフライパンを置いても変色・変形しません。また、吸水性がないため、汚れが染み込むことなく簡単に拭きとることができて、お手入れ楽々です。 汚れがスムーズに流れる「スキットシンク」は、シンク奥に段差が設けられていて、素早く水が流れていくよう設計されています。それにより汚れの広がりが抑えられ洗い物あとのシンク掃除が簡単に! 2段のレーンを活用してさざまな作業が手際よく行える「Wサポートシンク」はシンク内にレールがあり、スライド式のプレートを引き出せて、ワークトップを汚しやすい揚げ物の下ごしらえや肉・魚のカットなどをシンク内で行うことが可能。また洗い物の水切りなど作業に応じてシンク内のスペースを活用できて、調理も片付けもWでサポートしてくれます。 株式会社 LIXIL LIXILのキッチンは収納力も魅力のひとつ。「リシェル」ではテコの原理で、引き出しを開ける力を約30%軽減したという「らくパッ収納」でさらに使いやすさがアップ!立体構造で無駄なく収納スペースが活用できるようになっています。 10.毎日子どもと一緒に入るバスタイムの充実と、機能性もデザイン性も欲張りたい! お風呂は一日の疲れを癒したり、家族とのコミュニケーションを育む場であったり、大切な空間です。ご自身のライフスタイルに 合ったお風呂を設置することで、満足度の高いバスタイムを毎日過ごすことができます。 編集部がご紹介するパナソニックの「オフローラ」は、「シンプルって、自由」がコンセプトのシステムバス。当たり前にあったカウンターや棚をなくすことですっきりとしたデザインと、お手入れのしやすさが実現されています。洗い場のスペースが広々と使えて、子ども達とのびのびお風呂タイムが過ごせます。 Panasonic 天井に埋め込まれ凸凹のない「フラットライン照明」、表面が硬くなめらかで拭くだけで綺麗な状態を保つことができる「スゴピカ浴槽」、水垢が付きにくい新素材で作られた「スゴピカ水栓」、床はスミが少し立ち上がってコーナー部に目地がなく、スミまでラクに拭くことができる「スゴピカフロア」が標準仕様の「オフローラ」は、浴室まるごとお手入れしやすくなっています。壁パネルも選べる幅が広く、デザイン性も高い空間を演出できます。そこに自分好みのアイテムをプラスすることで、ご自身のライフスタイルに合わせてお風呂を組み立てていくことができるのも大きな魅力。 オプションでつけられる「酸素美泡湯」は、酵素を含んだミクロ泡がお湯を白く柔らかくし、湯冷めしにくく体を芯から温めてくれます。モイスチャー効果もあり、肌のうるおいが保たれしっとり感が長続き。バスタイムをどう過ごしたいかを考えて、選ぶのは楽しいですね。 11.雑誌で室内窓をみて、素敵だったので作ってみたいです!室内窓にはどんな効果がありますか? 𠮷川住研 室内窓は、見た目がおしゃれなだけではなく、立地条件や間取りによって、窓の取れない部屋や奥まった部屋であっても、室内窓で日当たりのいい部屋とつなげて明るさを採り、風の抜けも確保できます。 また、室内窓を設けることで空間のつながりが緩やかになり、別々の場所にいながら家族を近くに感じることができます。 12.大きなダイニングテーブルを置いて、リビングを作らない間取りは可能ですか? 輪和建設株式会社 もちろんできます!最近ではダイニングとリビングが一体化した、リビングを設けない間取りを選ぶ人も増えているようです。 リビングを作らないことで、空間に余裕をもってダイニングを作るということもできますし、間取りの選択肢も増えます。ダイニン グを中心に家族と過ごす空間を考え、食事をしたりくつろいだり、家族団らんの場として大きなダイニングテーブルを配置するのは素 敵ですね!キッチンカウンターとダイニングテーブルをつなげて配置すると、配膳や後片付けなどの家事動線も楽になります。 まとめ>> いかがでしたでしょうか? 家づくりで大切なことは、「思い描いている暮らしのイメージや、かなえたい生活スタイルを作り手に伝えること」。 人生を過ごす住まいについて、家族や住宅会社、相談カウンターなどで思う存分話してください!そして、マイホーム実現への過程を楽しむことも重要です! 「奈良すまい図鑑WEB」では、県内の優良住宅会社が掲載されています。是非、ご自身のこだわりを見つけて、どの住宅会社が自分に合っているか検索してみてください!

